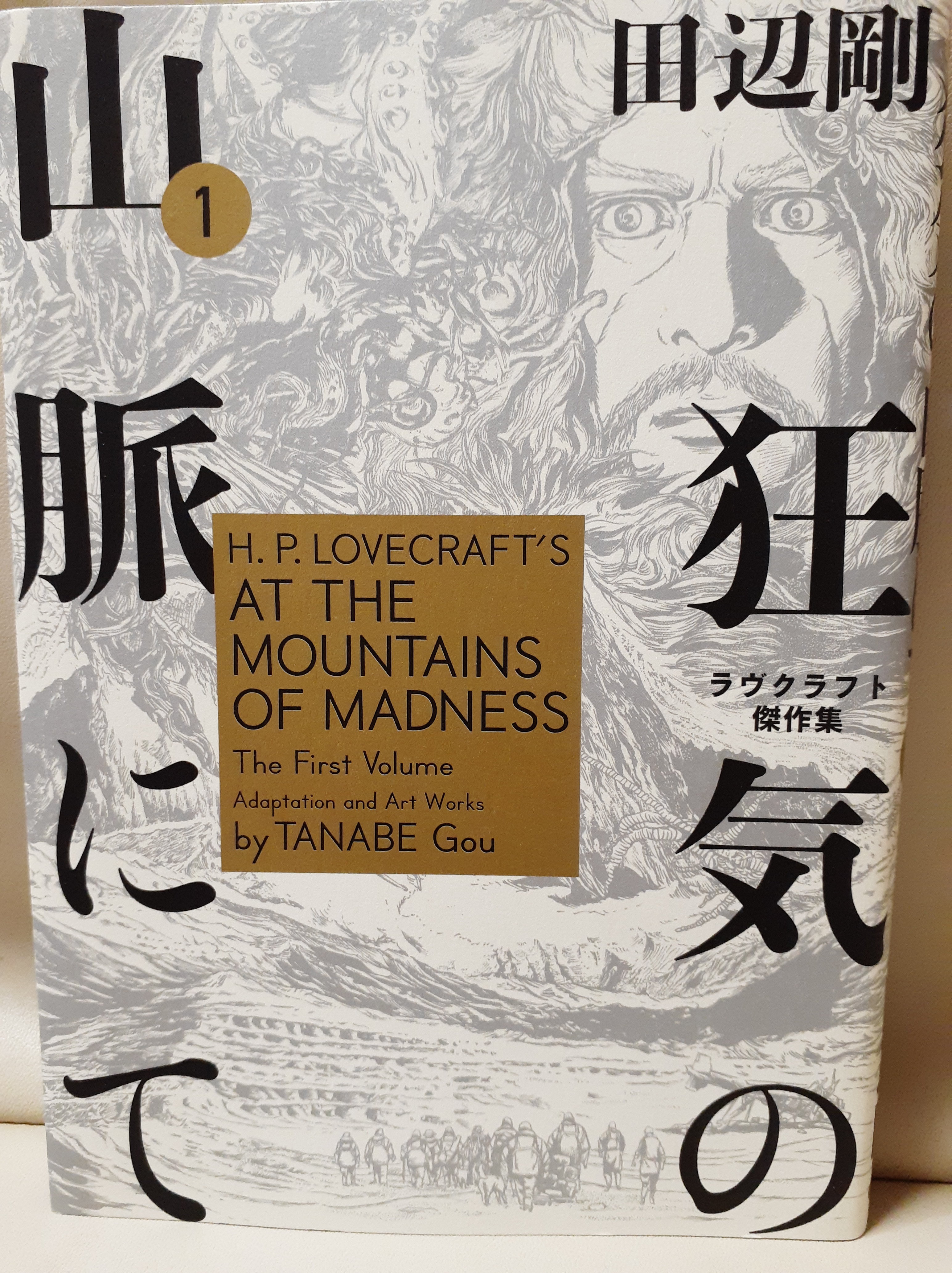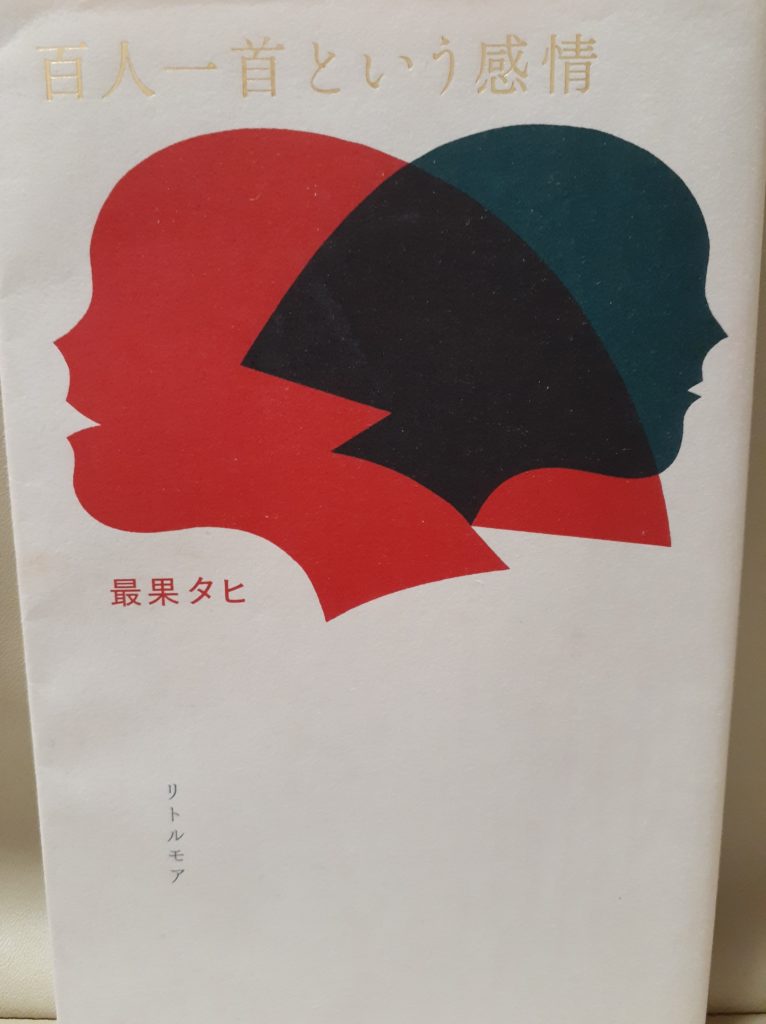
このエッセイの著者、最果タヒさんについて
最果タヒ(さいはてたひ)さんは、学生時代に詩人としてデビューを果たし、詩以外に小説やエッセイなどでも活躍されています。
2005年、『現代詩手帖』2月号の新人作品欄に初投稿で入選。
その後も投稿を続け、2006年に優秀な投稿者に送られる第44回現代詩手帖賞を受賞。
2007年、第一詩集『グッドモーニング』を上梓。
2008年、京都大学在学中に『グッドモーニング』で当時女性では最年少の21歳で第13回中原中也賞を受賞されました。
その後も作品を発表し続け、第四詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』は映画化もされました。
私は『もぐ∞』というエッセイで最果さんの文章にどハマり。
どうしても10代が読んでいるイメージがあったので、自分は読んでも共感できないと思い込んでいたのですが、今では、今回ご紹介する『百人一首という感情』をカフェに持っていき、読んでるうちに心の棘がとれて楽になるという行動に味をしめています。
人の想いや手垢や時の流れでくちゃくちゃになりながら、今、ここにある言葉。
その言葉達を丁寧にすくい取って見せてもらってるみたい。
それが心地よくて、心洗われるようでスーッとする。
今回の本は、『百人一首という感情』
エッセイです。
百人一首を詩の言葉で訳して欲しい、という依頼があって出来上がった本。
千年前の百人一首に対しても、最果さんの解釈は言葉や人に対する愛情が溢れているように感じられて、たまに泣きそうになります。
一部ですが、ご紹介していきますね。
花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
世界三大美女、小野小町の歌です。
「桜の花の色は、長雨が降る間に、いたずらに色あせてしまった。私の美しさもまた、色あせてしまっていた。さまざまなことを思い悩んでいるうちに」
キレイで美人でもてはやされた人が、桜の花の色が色あせたことと自分の容姿が年齢とともに変わったことを重ねているんだなぁ、と、わかりやすい歌だと思います。
ナルシストな雰囲気も感じたりして。
とにかく美しいお姫様、ということで、百人一首の札を使った“坊主めくり”では小野小町をとったらちょっぴり嬉しいっていう存在(笑)
逆に人気のないのはお坊さんの蝉丸。
なんでかなー。
ごめんね、蝉丸。
話を小野小町の歌に戻します。
タヒさんがこの歌に感じたことが、『百人一首という感情』には丁寧に描かれています。その一部を以下にあげます。
勉強として百人一首に向き合っていたころ、それは言葉を分解していく作業だった。その歌がどのように素晴らしくて、この31文字の中に、ぎゅっと意味を詰め込み、それを美しく見せているのか、理解するためには必要なことだった。けれど、その歌を詠んだ作者達が、そうしたことを逆算ですべてやっていたかというと、それはどうも違う気がする。まず、彼らをつきうごかした「この瞬間を詠みたい」という衝動があったはずで、その感性が羽ばたく瞬間、それにつられ、彼らの技術が花開いただけに過ぎない。私はそれに誠実になりたかった。詩の言葉でなら、そこまで行けないだろうか。そこまで、行かなくてはいけないのではないか。
千年前の人々の「この瞬間を詠みたい」という衝動に、限りなく近づこうとしているのでしょうか。
詩の言葉で。
タヒさんの静かな気迫のようなものを感じて、私は何度も泣きそうになります。
天つ風 雲のかよひ路吹き閉ぢよ 乙女の姿 しばしとどめむ
申し訳ないけれど、私はこの歌をずっと、
“カワイイ踊り子さんたち、行かないでおくれよぉ。あの子達の帰り道が通れなくなってしまえばいいのに。カワイイ子をもっと見ていたいよぉ”
って歌に感じられて、エロおやじ何言ってんのって思ってました。
「天の風よ、雲の中にある、天女たちの通り道を、どうか吹いて閉じてくれ。少女たちのうつくしい舞をもうすこし、ここに留めておきたい」
なんかごめん。
タヒさんにかかれば違う。
踊る人をみつめているとき。踊るその人は、たしかに人間なのに、なにか本質的な部分が、自分とずれてしまっているように見える。そういえば人とそっくりな姿をしたロボットは逆に不気味に見えるんだっけ?そういうものに近いのかもしれない。人間に近づいたロボット、とは違って、踊る人は、人間よりも神様に近い感じだろうか。人という存在の、精度を高め過ぎて、人ではなくなっていくような、そういうもの。踊りはじめると、似ていても、語り合えても、近くても、その奥には違うものがあるように感じる。ロボットであれば不気味かもしれない、しかしこの場合、私たちは引き込まれる。むしろ私たちがロボットで、彼女を目指して生きてきたかのように、引き込まれてしまう。
踊りの神秘性は、人を人でなくすかのように、いや、そもそも、最初から人ではなかったのではないか?などと自分の思考が曖昧になっていくような、そんな別の世界を垣間見るきっかけとなるものかもしれません。
少女を天女にたとえているのは、その舞の見事さを讃えるためでもあったのだろうけれど、そうした「人ではない存在」を、踊る人の体内に感じてのことかもしれない、とも思う。ただ女性として美しかったから、舞が見事だったから、華美なたとえを使ったというだけではないように思う。踊るひと、ただ右から左へと動いていくだけなのに、どうして、その手に、足に、瞳に、風の誕生を感じてしまうのか。雲さえも彼女たちの動きに従うように思えてならない。地上で舞っている彼女たちに、地上はどうしても似合わない、重力から解放されて、大地から旅立って、空で、舞っているほうがずっと似合うはずだった。それでもここにいて欲しい、私を圧倒してほしい、それを喜びとして感じられることが、人である自分への肯定のように思えてならない。
自分が、いつまでこういうことに感動していられるだろうって考えることありませんか?
時の流れ
状況の変化
気持ちの移ろい
様々な要因で、全く同じ自分で居続けることは出来ないから、かつてこういう風に感じてた自分は今はもういなくて、意図せずとも昔とは違う感じ方をしている。仕方ないことだけど、かつての自分の感じ方がもう一度蘇ってきたらいいのに。
なんて考えませんか。
たいていは、昔と違っても構わない感じ方がほとんどと思います。
でもまれに、保ちたい、取り戻したいって感じ方があるはず。
自分の中で変えたくない部分。
でも変わってしまう部分。
そういうものへの名残惜しさ、大切にしたいのにすり抜けていく寂しさも今はこの歌に感じるようになりました。
成長したかな?
まとめ
詩の言葉で百人一首を訳すことに挑戦したタヒさん。
もともと、そういうことを考えたことは一度もなかったようです。
また、詩の言葉ですでにある作品をなぞっていくこと、訳していくことの想像がなかなかできないでいたとも書かれています。
ですが、ふと、百人一首だって本当は詩の一つだったはずと思う瞬間があり、勉強として正解を見つけるために読んでいた百人一首に詩の言葉で訳そうと向き合った途端、一気にすべてがほどけていき、詩として正しさも間違いもない、あいまいな感情や感覚が、自然が、まどろみがこぼれていったとも振り返られていて、私はそんな、タヒさんの詩の言葉で解釈された百人一首を読めてとても満足したし、ところどころに出てくるタヒさんの詩に対する真摯な姿に感動しました。
これから自分も、言葉というものをもっと真剣に楽しく、掘り下げていきたいと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。